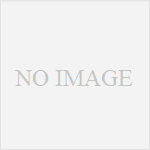堀越公方の誕生物語をカンタンに説明します。
小学生でも分かるかな?
スポンサーリンク
堀越公方とは
堀越公方とは室町幕府の重要な役職の一つ。
関東を統治するための幕府の主張所みたいなものです。
幕府のある京都と関東ではちょっと距離がありますからそのままでは目が行き届かない事がよくあるんです。
そこで、現地に居座って関東を見張ってくれる人が必要になります。
…で、堀越公方の登場。
本当は、、堀越じゃなくて鎌倉で公方をやるつもりだったのです。
しかし、実際に鎌倉に辿り着けなかった為、堀越(静岡県の伊豆)を拠点にする事にしました。
なんだか、中途半端な感じになってしまいましたが、これに至るにはちょっとした戦国のドラマがあったのです。
スポンサーリンク
堀越公方 あらすじ
鎌倉公方の滅亡
もともと関東には鎌倉府という室町幕府の出先機関がありました。
(鎌倉府の一番の責任者 → 鎌倉公方)
そこで、関東の大名の勢力を統治する役目を担っていたのです。
しかし、その鎌倉府の4代目の鎌倉公方(足利持氏、もちうじ)が幕府とケンカしちゃいまして、そしてケンカに負けて…追いつめられて…自害。
よって、鎌倉府は滅亡。
これを「永享の乱」(1438年)といいます。
とこが今度は、その3年後に鎌倉公方を滅ぼした将軍「足利義教」が暗殺されます。
※足利義教(6代目将軍よしのり、信長タイプの武将)
鎌倉公方が再出発。だけど…
すると、鎌倉公方を目の敵にする人がいなくなったので、鎌倉公方を復活させようとする動きが出て来ました。
そこで、新たな鎌倉の足利成氏(しげうじ)が登場します。
成氏は先代の鎌倉公方、足利持氏の息子さんです。 (←よく生きていましたね、殺されずに)
一度滅ぼされた鎌倉公方でしたが、地元の武士や有力者の間では鎌倉公方の再来を望む声もあり、幕府は鎌倉公方の再設立OKのサインを出します。
とは言ってもこの時、足利成氏は3歳のお子ちゃま。
形だけの公方です。
鎌倉公方の仕事はまだ出来ませんが、公方が生きている…と言う事に意味があったんでしょうね。
シンボルとしての公方。
実際の関東地域の統治は関東管領の上杉氏が行っていました。
さて、そんなお子ちゃま公方も、大人になるとだんだんと本物の公方らしくなって来ます。
成氏は、かつての鎌倉公方ファンの応援も受けながら勢力を伸ばして行く。
そこでまた、鎌倉公方と上杉氏が対立関係となり、合戦や流血事件などが起こり始めるのです。
これを見た室町幕府は「やっぱ鎌倉公方がいると争いの元になる、ダメだこりゃ」
と判断します。
そして軍勢を派遣して、駿河の今川氏と合流し鎌倉公方を攻めました。
ただでさえ、上杉氏と争っているのにさらに幕府軍が襲いかかってくるとは…公方としても、とても太刀打ちできない。
古河公方?だれですか?あなた。
そこで、鎌倉公方は関東の北方面に逃げて行きました。
今の茨城県の古河市(こがし)へ。
(「古河」と言う地名は昔から変わらないのですね…)
以降、成氏はここを拠点にして皆から「古河公方」(こがくぼう)と呼ばれるようになります。
すると今度は、鎌倉公方の領域に上杉氏が入り込んで来て領地を拡大します。
これも室町幕府のから見たら困るんです。
上杉が強過ぎてしまうから。
それに逃げた古河公方だって、充電してパワーアップしてきたらあとあと面倒な事になるぞ…。
そこで室町幕府は「やっぱ鎌倉公方はいた方が良い、できれば幕府に従順な人なら◎」
と言うことで新たな鎌倉公方を作る事にします。
今度こそは上手くいくぞ、将軍の弟だから
新公方を担当するのは将軍の弟「足利政知」(まさとも)でした。
政知の兄さんは室町8代将軍の足利義政(よしまさ)。
「銀閣寺」の義政、「応仁の乱」の義政です。
そんな義政兄さんに頼まれて、軍勢を従えた新公方「足利政知」は関東の地を目指します。
政知の一発目の仕事は「自称古河公方」の足利成氏をやっつけること。
公方が2人もいたらややこしくて困りますからね。
我こそが本物の公方だ!と示さねばなりません。
ところが・・・です。
関東は恐ろしい所だった
京都を出発した足利政知は古河公方を討つどころか、鎌倉にさえ辿り着けません。
関東の大名にとっては、新しい統治者がやって来るなんて面倒くさい監視人がくるようなものですから、受け入れたくないんです。
それに今後、古河公方がうっとおしくなったら、自分達でやっつけちゃえば良いんですから。
「べつに、政知なんかいらないよ」そんな空気でした。
しかも、関東の大名は猛者ばかり。
とりあえず、今川、武田、上杉。
怖いんです、この人達。
そして、負けて逃げたはずの古河公方ですが、予想以上に勢力が残っていて、意外と強い。
さらには、もう少し小さい勢力達もしのぎを削って現地で頑張っています。
幕府の軍団だからって、そう簡単に通してくれません。
黙って領地を通過しようものなら大変な目に合います。
「おい、おまえら何者だ?ここは誰の縄張りだと思ってんだ」と因縁をつけられ
「僕ら幕府の者なんですが、これから古河公方を倒しに行くんです〜」と説明しても
「そんなの聞いてないぞ、帰れ帰れ」となります。
こんな調子では、とても茨城県まで辿り着けません。
かつての幕府が強かった時代とは違って、簡単に道をあけてくれないのです。
堀越公方の誕生
…で政知さんは考えました。
こんなの絶対に無理。
この状態でどうやって古河まで行くんだよ?
もう限界。
頑張ってもせいぜいここまで。
そしてそこは伊豆の国、堀越でした。
(堀越 → ほりこし。マニアックな人は「ほりごえ」といいます)
現在の静岡県の伊豆市です。
それ以降、政知は堀越を拠点とし堀越公方と呼ばれるようになりました。
関東は古河と上杉と堀越
…で結局、足利政知は、、、当初の目的である「古河公方の討伐」は果たせず伊豆に御所を構えます。
しかし、これはこれで絶妙なバランスが成り立ちました。
関東の東側を古河公方。
真ん中を上杉。
西側を堀越公方。
それぞれの者がそれぞれの地域を治めます。
そして、問題の古河公方は幕府と「和睦する」という形で決着がついたのです。
戦わずして、相手を尊重しながら、幕府に従わせる事ができました。
うむ、結果オーライ。
政知さん、京都から来てくれてありがとね。
まとめ
室町幕府の関東の出先機関であった鎌倉府。
しかしそれは、幕府の信頼を失い一度は滅亡。
その後また鎌倉府は再興を計りますが今度は上杉氏と対立。
そこでまた鎌倉府を滅ぼします。
しかし、鎌倉府が無いと上杉氏が強くなり過ぎる。。。
そこで登場したにが「堀越公方」。
本当は新鎌倉公方でやっていくつもりでしたが、意外な展開から堀越公方が誕生します。
堀越公方は鎌倉公方の失敗作かと思いきや、対立関係にあった古河公方と室町幕府を
和睦と言う形に導いてくれました。
一応、ある程度のの存在価値はあったようです。